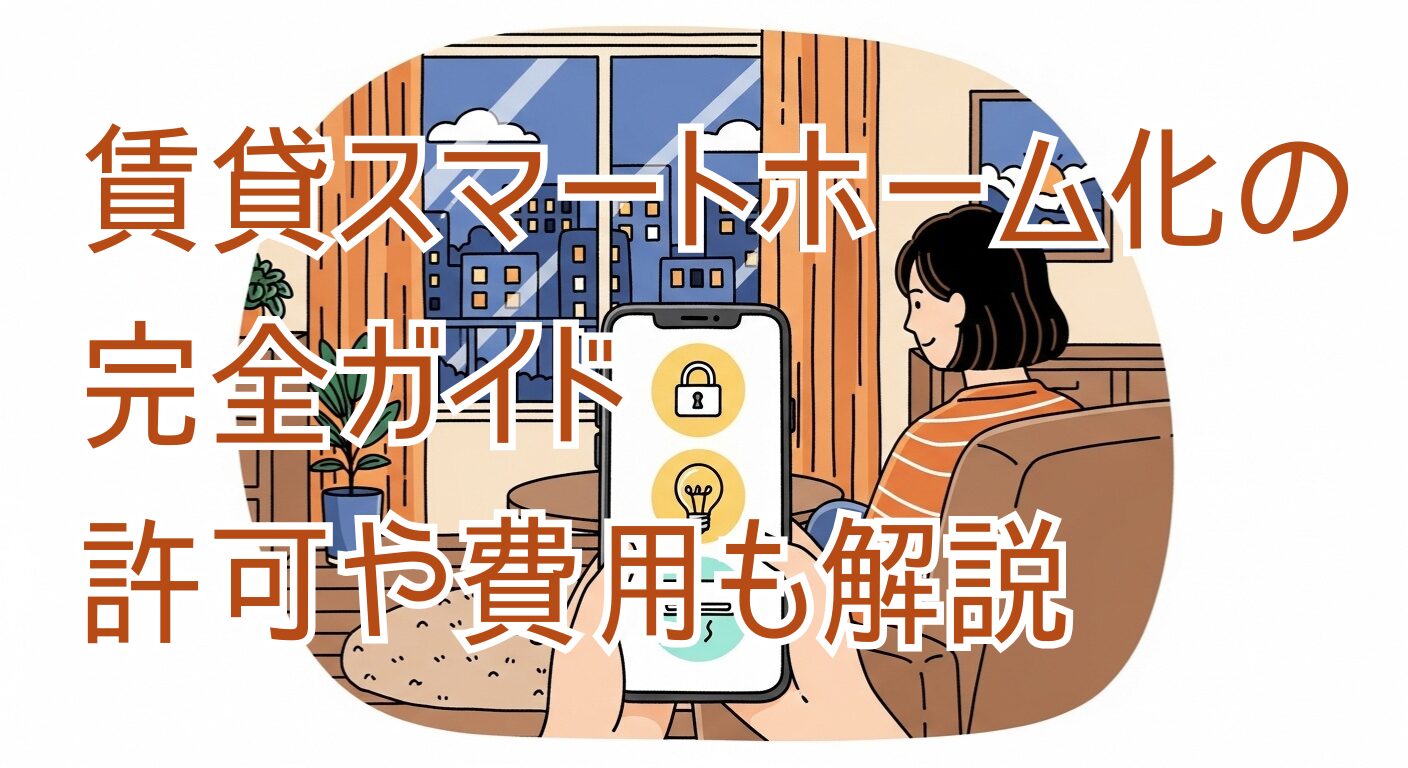最近、本当に便利になったスマートロック。鍵なしで家に入れる手軽さは、一度体験すると戻れないほど魅力的ですよね。僕も「賃貸の自宅に後付けしたい!」と本気で考えた一人です。
でも、賃貸だと「原状回復」の義務があります。スマートロックを設置したいけど、退去時にトラブルになるのは怖い。勝手に設置してバレるのが不安、そもそも許可は必要なのか、デメリットはないのか、おすすめの製品はどれか、そして両面テープの跡は本当にキレイに取れるのか…悩みは尽きません。
この記事では、そんな賃貸でのスマートロック設置に関する疑問や不安を解消するため、原状回復のルールから、管理会社への許可の取り方、そして安心して使える製品の選び方まで、詳しく解説していきます。
記事のポイント
- 賃貸でスマートロックを設置する際の基本ルールと原状回復の定義
- 管理会社や大家さんへの具体的な許可申請プロセスと伝え方のコツ
- 原状回復が簡単で賃貸に最適な「工事不要タイプ」の選び方
- 退去時に焦らないための正しい設置方法とキレイな取り外し方
賃貸でスマートロック設置は可能?原状回復の基本ルール
「賃貸だから」と諦めていたスマートロックですが、実際のところどうなのでしょうか?まずは、賃貸物件における設置の可否と、キーワードとなる「原状回復」の基本ルールについて見ていきましょう。
結論:工事不要タイプならOK!ただし「許可」が必須
いきなり結論からお伝えします。賃貸物件でもスマートロックを設置することは可能です!
ただし、それには絶対的な条件があります。それは、必ず事前に管理会社や大家さんから許可を得ること。そして、工事不要で原状回復が容易な「両面テープ固定式」を選ぶことです。
ドアに穴を開けたり、鍵のシリンダーごと交換したりするタイプは、建物の改変にあたるため、まず許可が下りません。無断で設置してしまうと、賃貸契約違反となり、退去時に大きなトラブルに発展する可能性があります。
2020年民法改正と「原状回復」の本当の意味
「原状回復」と聞くと、「入居時と全く同じ状態に戻すこと」だと思いがちですが、実は少し違います。
2020年4月の民法改正で、このルールは明確化されました。原状回復とは、「入居者の故意・過失や、通常の使用を超えるような使用による損耗」を復旧すること、とされています。
ポイントは、普通に生活していて生じる経年劣化や通常損耗(例:壁紙の日焼けなど)は、原則として大家さん負担であり、入居者が費用を負担する必要はない、ということです。
スマートロックに関して言えば、「両面テープ固定式」を「説明書通りに正しく設置」し、「退去時にドアを傷つけずにキレイに取り外す」ことができれば、それは故意の損傷には当たらず、原状回復の義務(=修繕費の請求)は発生しない、と解釈できます。

だからこそ、許可を得ることと正しい製品選び・設置・撤去が何よりも重要になるんですね。
【最重要】管理会社・大家さんへの許可申請プロセス
賃貸でスマートロックを導入する上で、最大のハードルであり、最も重要なのが「許可取り」です。ここを疎かにすると、後で必ずトラブルになります。どうやって連絡し、何を伝えればスムーズに許可が下りるのか、具体的な流れを解説します。
なぜ許可が必要?無断設置(勝手に・バレる)のリスク
「両面テープで貼るだけだし、バレないのでは?」「勝手に付けちゃダメなの?」と思う気持ちも分かります。しかし、無許可での設置は絶対にやめてください。
- 契約違反の発覚: 定期点検や他のトラブルで管理会社の人が入室した際、無断設置が発覚するケースがあります。最悪の場合、契約解除や損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。
- 退去時の高額請求: 「バレなかった」としても、退去時の立ち会いで必ず発覚します。テープ跡が残ったり、塗装が剥がれたりしていた場合、ドアの修繕費用や交換費用として高額な原状回復費用を請求されるリスクがあります。
- 管理上の問題: 万が一の火災や緊急時、管理会社が物理鍵で開けられない(スマートロックが誤作動している等)事態になると、安全上の大きな問題となります。
「バレるかどうか」ではなく、ルールとして許可が必要だと認識することが大切です。
ステップ別:許可申請の具体的な流れ
では、どうやって許可を取れば良いのでしょうか。僕は以下のステップで進めることをお勧めします。
ステップ1:事前準備(設置情報の整理)
管理会社に連絡する前に、伝えるべき情報を整理しておきます。「何となく付けたい」ではなく、「この製品を、こう付けたい」と具体的に伝えることが信頼に繋がります。
- 設置予定の製品名・型番(例:SwitchBot Lock Pro)
- 取り付け方法(「工事不要の両面テープ固定式である」こと)
- 原状回復の方法(「退去時はキレイに剥がして元通りにする」こと)
- 緊急時の対応(「物理鍵も併用可能である」こと)
製品のカタログやメーカー公式サイトのURLを控えておくと万全です。
ステップ2:管理会社へ連絡(電話またはメール)
準備ができたら、管理会社や大家さんに連絡します。
(伝え方の例)
「お世話になっております。入居者の〇〇です。防犯対策と利便性の向上のため、玄関ドアにスマートロックの設置を検討しています。設置したいのは、工事不要で両面テープで貼り付けるタイプで、退去時には必ず取り外して原状回復します。設置を許可いただくことは可能でしょうか?」
ポイントは、「防犯目的」であること、「工事不要」であること、「原状回復する」意志を明確に伝えることです。

大家さんや管理会社が心配しているのは、突き詰めれば「ドアを傷つけられないか?」と「退去時に本当に元通りになるか?」の2点だけです。この不安を払拭する説明を心がけましょう。
ステップ3:資料提出(求められた場合)
「製品の資料を送ってほしい」と言われたら、ステップ1で準備した製品カタログやURLを送りましょう。メーカーが「賃貸OK」と謳っているページがあれば、それも併せて送ると説得力が増します。
ステップ4:書面での許可取得(最重要)
電話や口頭で「いいですよ」と言われた場合でも、それで安心してはいけません。
必ず、メールや書面(契約書の特約欄への追記など)で、許可を得た証拠を残してください。
(例:「先日ご相談したスマートロックの件、許可いただきありがとうございます。念のため、本メール(または書面)をもって許可の証憑とさせていただきます。」など)
担当者が変わったり、「言った・言わない」のトラブルになったりするのを防ぐため、これは必須の作業です。
賃貸に最適!原状回復しやすいスマートロックの選び方
無事に許可が出たら、次は製品選びです。許可が出やすい=原状回復しやすい製品を選ぶことが、賃貸生活を快適にする鍵です。ここでは、賃貸で選ぶべきタイプと、絶対に避けるべきタイプをハッキリさせておきましょう。
選ぶべきは「両面テープ固定式」一択
賃貸住宅で選ぶべきスマートロックは、「両面テープ固定式」これ一択です。
これは、ドアの室内側にあるサムターン(鍵のつまみ)の上から、スマートロック本体を強力な両面テープで貼り付けるタイプです。
- 穴あけ工事やシリンダー交換が不要
- DIY初心者でも10分程度で設置可能
- 退去時は剥がすだけで原状回復できる
最近の主流はこのタイプで、大手メーカーの製品(セサミ、SwitchBot、Qrio Lockなど)の多くが対応しています。
絶対NG!賃貸で避けるべき製品タイプ
逆に、賃貸では絶対に選んではいけないタイプもあります。
- ドアに穴を開けるタイプ
- これは完全に「改変行為」にあたります。原状回復は不可能(または高額)なため、許可が下りることはまずありません。
- 鍵穴(シリンダー)ごと交換するタイプ
- これも同様に許可は得られません。無断で交換した場合、退去時にシリンダーの交換費用を全額請求されることになります。
安易に選んでしまうと、退去時に取り返しのつかないことになるので、必ず「両面テープ固定式」を選んでください。
賃貸向けおすすめ人気モデル比較
「両面テープ固定式」の中でも、特に人気があり、賃貸での実績も多いモデルをいくつかピックアップしてみました。僕が今注目している製品たちです。
| 製品名 | 価格目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| SESAME 5 (セサミ) | 約4,000円台〜 | 圧倒的なコストパフォーマンス。コンパクトで、Suicaなど交通系ICカードや指紋認証にも対応(別売オプション)。 |
| SwitchBot Lock Pro | 約18,000円程度 | 機能全部入りのオールインワンモデル。指紋認証、NFC、暗証番号など解錠方法が多彩。耐久性も高いと評判です。 |
| Qrio Lock (Q-SL2) | 約24,800円程度 | 国内メーカーの老舗。動作の安定性とセキュリティに定評があります。遠隔操作には別売りハブが必要です。 |
上記の価格や機能は、あくまで筆者が調査した時点での一般的な目安です。新モデルの登場やセールによって変動することがあります。
また、ご自宅のドアやサムターンの形状によっては設置できない場合もあります。購入前には、必ずメーカー公式サイトで最新の価格・機能・対応可能なドアの形状を確認してください。
退去時に慌てない!原状回復のための設置と撤去術
製品を選んだら、いよいよ設置です。しかし、ここで焦ってはいけません。「設置の時」から「退去時のこと」を考えて作業するのが、賃貸上級者です。ドアを傷つけず、退去時に跡形もなく撤去するためのコツを解説します。
設置時の重要チェックポイント(設置前の準備)
購入前に、まずはご自宅のドアが本当に対応しているかを確認します。
- サムターンの形状: つまみの形は様々です。メーカーの対応表を見て、自分の家のサムターンに対応しているか確認しましょう。
- 設置スペースの測定: サムターンの周囲に、スマートロック本体を貼り付ける十分な平面スペースがあるか、メジャーで正確に測ります。
多くのメーカーが、スマホで撮影した写真を送ると互換性を診断してくれる無料サービスを行っています。不安な方はぜひ利用しましょう。
接着力を最大化し、剥がれを防ぐ「脱脂」
無事に設置できることが確認できたら、いよいよ貼り付けです。両面テープの接着力を最大限に発揮させ、後で剥がれ落ちるトラブルを防ぐために、「脱脂(だっし)」が非常に重要です。
ドアの貼り付け面には、目に見えないホコリや油分が付着しています。これをそのままにしてテープを貼ると、粘着力が大幅に低下します。
- 貼り付け位置を決める。
- アルコール(消毒用エタノールなど)を含ませた布やキッチンペーパーで、貼り付け面をキレイに拭き取る。
- アルコールが完全に乾くまで待つ。
- スマートロック本体(またはマウント)を貼り付け、1分以上強く圧着する。
この「脱脂」と「圧着」の手間を惜しまないことが、安定した運用とトラブル防止に繋がります。
ドアを傷つけない!両面テープのキレイな剥がし方
そして、いよいよ退去の日。原状回復の総仕上げ、取り外し作業です。強力な両面テープで固定されているため、力任せに剥がすのは厳禁!ドアの塗装ごと持っていかれる可能性があります。
以下の手順で、慎重かつスマートに剥がしましょう。
コツ1:ドライヤーで温める
両面テープの粘着剤は、熱を加えると柔らかくなる性質があります。
ドライヤーの温風を、本体とドアの隙間に当てるように30秒~1分ほど当てて温めます。これにより、粘着力が一時的に弱まり、剥がしやすくなります。
コツ2:シール剥がしスプレーを使う(成分注意)
温めても固い場合は、市販の「シール剥がしスプレー」を使います。本体とドアの隙間に少しずつスプレーし、液剤が浸透するのを待ってから、ゆっくり力を加えます。
マニキュアを落とす「除光液」は、強力な溶剤であるアセトンを含んでいることが多く、これを使うとドアの塗装まで溶かしてしまう危険性があります。必ず「シール剥がし」専用の製品を使い、目立たない場所で試してから使用してください。
コツ3:ヘラやテグスで慎重に
隙間ができてきたら、プラスチック製のヘラ(傷がつかないもの)や、タコ糸・テグスなどを隙間に滑り込ませ、のこぎりのように動かしながら粘着面を切り離していくのも有効です。
焦らずゆっくり作業すれば、必ずキレイに剥がせます。
知っておきたいメリットとデメリット(トラブル対策)
「開けゴマ」とまではいきませんが、スマホ一つで施解錠できる生活は本当に便利です。しかし、便利なものには必ず裏返しもあります。賃貸で導入するからこそ知っておきたいメリットと、起こりうるトラブル・デメリットへの対策をまとめます。
メリット:鍵の紛失リスクゼロ、オートロックの安心感
僕が考える最大のメリットは、やはり「鍵」という物理的な束縛から解放されることです。
- 鍵の紛失リスクがゼロに: 「終電で帰宅したら鍵がない!」といった絶望的な事態がなくなります。
- 閉め忘れの不安解消: オートロック機能を使えば、ドアが閉まると自動で施錠。「あれ、鍵かけたっけ?」と外出先で不安になるストレスから解放されます。
- 一時キーの発行: 友人や家族、家事代行サービスなどに対し、一時的に有効なデジタルキーを発行できます。物理的な鍵の受け渡しが不要になり、非常に便利です。
デメリットと対策:電池切れ、閉め出しリスク
もちろん、デメリットもあります。特に賃貸では、トラブル=管理会社への連絡、となりがちなので、事前に対策が必須です。
主なデメリットと対策
1. 電池切れによる閉め出し
スマートロックは電池で動いています。電池が切れると、当然ながら動作しません。
【対策】
- ほとんどの製品は、電池残量が少なくなるとアプリで通知が来ます。通知が来たら絶対に放置せず、すぐに電池交換しましょう。
- 万が一の閉め出しに備え、物理鍵も必ず1本は持ち歩く(カバンや財布に入れておく)ことを徹底してください。
2. アプリ不具合・スマホ故障
スマホの電源が切れた、スマホを紛失した、アプリが不具合を起こした…など、デジタルならではのトラブルです。
【対策】
- やはり「物理鍵」の併用が最強のバックアップになります。
- 指紋認証や暗証番号パッドなど、スマホ以外の解錠手段(別売オプションの場合あり)を併用するのも有効です。
よくあるトラブル事例と対策(剥がれ・エラー)
その他、実際に使ってみて起こりがちなトラブルと対策も知っておきましょう。
トラブル1:両面テープが剥がれてきた
原因は、設置時の「脱脂」不足や「圧着」不足がほとんどです。また、ドアの素材と両面テープの相性が悪い場合もあります。 【対策】設置時にアルコールでの脱脂と圧着を徹底すること。剥がれてしまった場合は、再度脱脂し、メーカー純正の強力な交換用テープで貼り直しましょう。
トラブル2:アプリや本体のエラー
急に反応しなくなった、エラーが出るなど。 【対策】まずはアプリや本体ファームウェアを最新版にアップデートしましょう。メーカーのサポート体制(チャットや電話)が充実している製品(SwitchBotなど)を選ぶと、いざという時に安心です。
まとめ:正しい手順で賃貸でもスマートロックは楽しめる!
最後に、賃貸物件でスマートロックを導入するためのポイントをおさらいします。
- 【最重要】必ず事前に管理会社・大家さんの「書面許可」を取る。
- 製品は「工事不要」で「両面テープ固定式」のタイプを選ぶ。
- 設置時は「脱脂・圧着」を徹底し、退去時は「温めて」丁寧に剥がす。

賃貸だからと諦める必要はありません。「事前の許可」と「原状回復しやすい製品選び」という2つのポイントをしっかり押さえれば、賃貸でも安全・快適なスマートロック生活を送ることは十分に可能です!