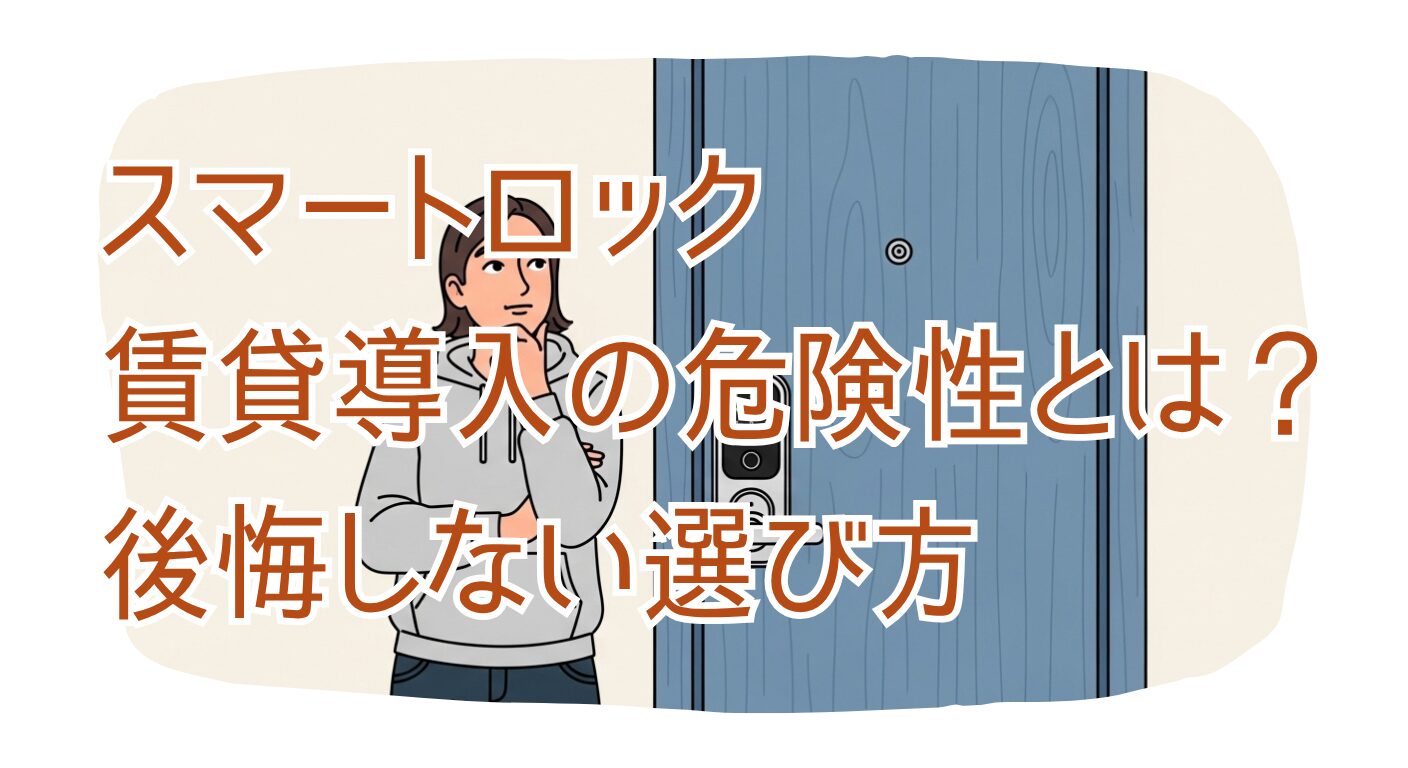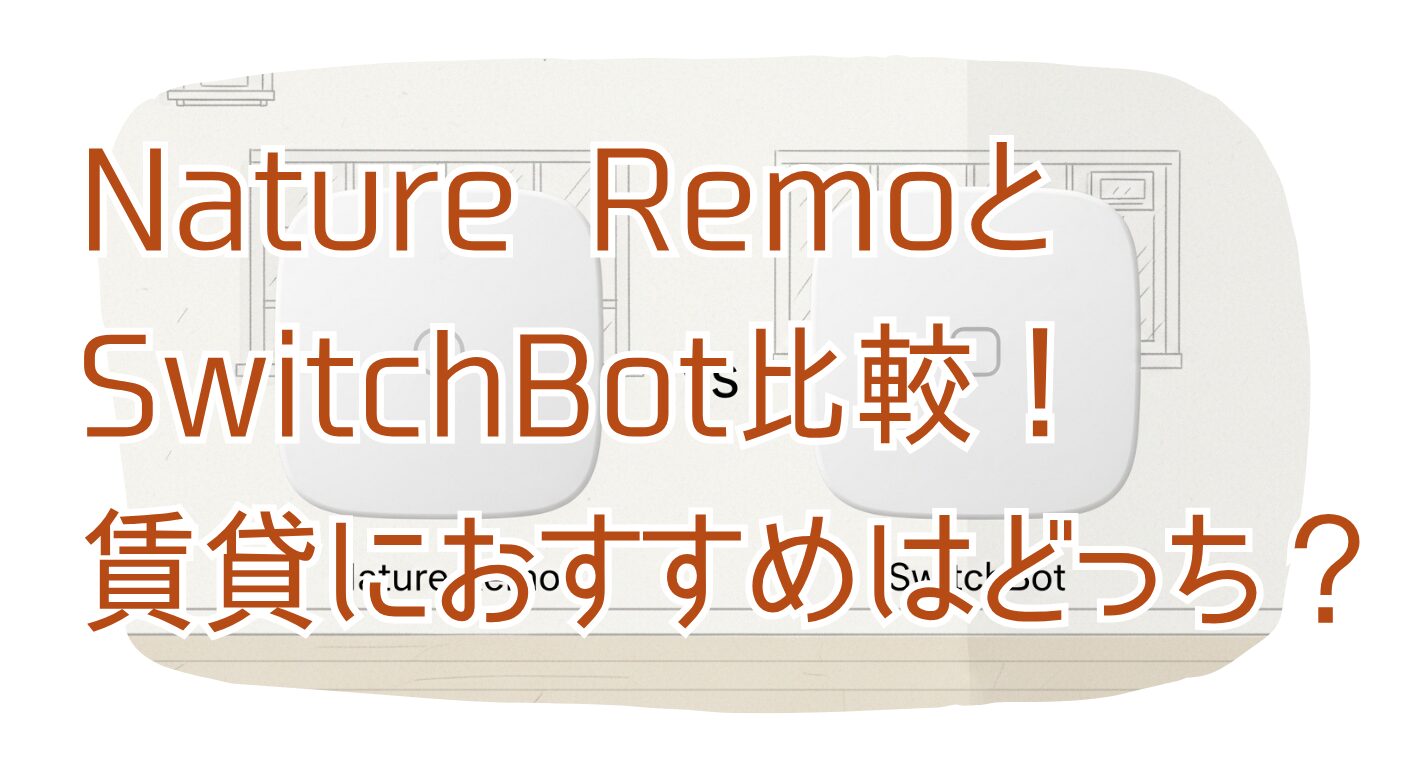賃貸物件に住んでいると、鍵の持ち運びや閉め忘れの不安を感じることはありませんか?そんな悩みを解決してくれるのがセサミのスマートロックですが、賃貸での取り付けや原状回復について気になる方も多いはずです。

僕も最初は壁やドアを傷つけないか心配でした。
実際に調べてみると、オートロックやアプリ連携など便利な機能がたくさんあることが分かりました。この記事では、賃貸住宅でも安心して使えるセサミスマートロックの魅力や導入方法を詳しく解説していきます。
記事のポイント
- 賃貸でも工事不要で簡単に取り付けられる仕組み
- オートロック機能や他社製品との比較ポイント
- セサミ5とProの違いや自分に合うモデルの選び方
- 退去時に跡を残さずきれいに取り外す方法
セサミスマートロックを賃貸で使うメリット
僕自身、賃貸暮らしの中で「もっと玄関を快適にしたい」と常に考えてきましたが、やはり壁に穴を開けるわけにはいかないのが最大の悩みでした。そこで注目したのがセサミスマートロックです。ここでは、なぜこの製品が賃貸ユーザーにこれほど支持されているのか、その具体的な理由とメリットについて深掘りしていきます。
工事不要で原状回復できる設置の仕組み
賃貸物件でスマートロックを導入する際、最も高いハードルとなるのが「設置方法」です。一般的な鍵の交換にはシリンダーの取り外しやドアへの穴あけ工事が必要なケースがあり、これらは管理会社や大家さんの許可を得るのが非常に難しいですよね。
しかし、セサミスマートロックの最大の特徴は、既存のサムターン(鍵のつまみ)の上から被せるように貼り付けるだけというシンプルさにあります。基本的には強力な3M両面テープを使用しますが、ドアの素材によってはマグネットでの設置も可能です。これにより、ドア自体には一切傷をつけずに固定できるため、退去時の原状回復トラブルを心配する必要がありません。
工事資格も特別な工具も一切不要。届いたその日に、誰でも数分で「オートロック付き物件」のような環境を手に入れられます。
対応する鍵の種類とアダプターの活用法
「うちの鍵は古いタイプだけど大丈夫かな?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、セサミは日本の住宅事情を徹底的に研究して作られています。その対応率は驚くべきことに99%以上と言われており、一般的なMIWAロックやGOALなどの鍵であれば、ほぼ問題なく取り付け可能です。
もし鍵のつまみが特殊な形状をしていたり、高さが合わなかったりする場合でも諦める必要はありません。メーカーであるCANDY HOUSE JAPANは、写真送付だけで3Dプリンターを使って専用のオーダーメイドアダプターを作成してくれるサービス(有料)を提供しています。
自宅の鍵の写真を撮ってメールで送るだけ。数百円程度で作成してくれるため、特殊な鍵でも安心して導入できます。
オートロック機能での締め出し防止対策
僕がスマートロックを導入して最も感動したのは「オートロック機能」です。ゴミ出しやコンビニへのちょっとした外出時、鍵を取り出して閉める動作から解放されるのは想像以上に快適でした。セサミでは、ドアが閉まった後の施錠時間を「3秒後」から「1時間後」まで自由に設定できます。
一方で、スマホを持たずに外に出てしまい、勝手に鍵が閉まって部屋に入れなくなる「締め出し」のリスクもゼロではありません。これを防ぐためには、以下の対策が有効です。
- ゴミ出し程度の外出でも必ずスマホを持つ習慣をつける
- 別売りのキーパッド(暗証番号や指紋で解錠できる機器)を設置する
- 物理鍵をカバンの中に常備しておく
本体のオートロック機能はタイマー式のため、ドアが開いたままでも時間が来ると鍵が回ってしまいます。確実な開閉検知を行いたい場合は、別売りの「オープンセンサー」の導入を強くおすすめします。
アプリでの合鍵シェアと権限管理の便利さ
家族や友人が遊びに来た際、合鍵を渡すためにわざわざ玄関まで行く必要はありません。セサミのアプリを使えば、相手にアプリをインストールしてもらい、QRコードを読み込んでもらうだけで簡単に「デジタル合鍵」を発行できます。
| 権限の種類 | できること | 想定利用シーン |
|---|---|---|
| オーナー | 全機能の設定・変更 | 契約者本人 |
| マネージャー | 施解錠、ゲスト招待 | 同居の家族・パートナー |
| ゲスト | 施解錠のみ | 友人・家事代行サービス |
このように権限を細かく設定できるほか、利用可能な時間を限定することも可能です。「毎週月曜日の10時から12時まで」といった指定ができるため、定期的な家事代行サービスや来客時にもセキュリティを保ちながら便利に使えます。
SwitchBotなど他社製品との比較
スマートロックを検討していると、必ず比較対象に挙がるのが「SwitchBotロック」や「Qrio Lock」ではないでしょうか。僕の視点で比較すると、セサミの最大の強みは「圧倒的なコストパフォーマンス」と「動作の軽快さ」にあります。
| 比較項目 | セサミ5 (SESAME) | SwitchBotロック Pro |
|---|---|---|
| 本体価格 | 約4,000円〜6,000円台 | 約12,000円前後 |
| サイズ | 超小型・軽量 | やや大きめ |
| スマートホーム連携 | Google/Alexa対応(要ハブ) | SwitchBot製品との連携に強み |
| 特徴 | とにかく安くて反応が爆速 | 家電全体を一括管理したい人向け |
もしあなたが「すでにSwitchBot製品で家中の家電を操作している」という場合はSwitchBotロックのほうがアプリを統一できて便利かもしれません。しかし、「まずは鍵だけ便利にしたい」「初期費用を抑えたい」という賃貸ユーザーにとっては、セサミのコスパは非常に魅力的です。
セサミスマートロックの賃貸への導入手順
ここからは、実際にセサミスマートロックを購入してから設置し、退去するまでの流れをシミュレーションしてみましょう。失敗しないためのコツや、長く使うためのメンテナンス方法についても僕なりの視点で解説します。
強力テープや磁石で確実に固定するコツ
セサミ本体が落下してしまうと、最悪の場合、家に入れなくなるリスクがあります。設置の際は、以下の手順で確実に取り付けることが重要です。
- 脱脂・清掃:設置面の油分や汚れをアルコールシート等で完璧に拭き取る。これが一番大事です。
- 高さ・位置合わせ:サムターンの回転軸とセサミの回転軸がズレないよう、中心を合わせて仮当てする。
- 圧着:両面テープで貼り付けた後、体重をかけて30秒以上しっかりと押し付ける。
また、賃貸物件でテープ跡が心配な方や、ドアが金属製の場合は、オプションの「強力マグネット」を使用するのがベストプラクティスです。これなら貼り付けミスをしても何度でもやり直せますし、取り外しも一瞬です。
セサミ5とProの違いや選び方を解説
現在販売されている主要モデルには「SESAME 5」と「SESAME 5 Pro」があります。どちらを選ぶべきか迷うところですが、結論から言うと一般的な一人暮らしや家庭用なら「SESAME 5」で十分です。
- SESAME 5:価格が安く(5,000円以下の場合も)、電池持ちが良い。通常の家庭利用(1日10回程度の開閉)なら全く問題ありません。
- SESAME 5 Pro:ブラシレスモーター搭載で耐久性が非常に高く、動作音が静か。オフィスやシェアハウスなど、1日に何十回も開閉する場所向けです。
Proモデルは縦長でスリムな形状をしているため、サムターンの横にスペースがない狭いドア枠の場合はProのほうが取り付けやすいこともあります。設置スペースの寸法を測ってから決めると良いでしょう。
ハブ連携による遠隔操作とスマートホーム
本体単体ではBluetooth接続のみとなるため、玄関の前まで行かないと操作できません。これをもっと便利にするのが、別売りのWi-Fiモジュール「Sesame Hub3」です。
ハブをコンセントに挿して連携させると、外出先から鍵の状態を確認したり、遠隔で施錠・解錠したりできるようになります。「あれ、鍵閉めたっけ?」と不安になったときに職場から確認できる安心感は代えがたいものがあります。また、Google HomeやAmazon Alexaと連携して「アレクサ、鍵を閉めて」と声で操作することも可能になります。
落下や電池切れ等のトラブル対処法
長く使っていると避けられないのが電池切れです。セサミは電池残量が少なくなるとアプリで通知してくれますが、万が一完全に切れてしまった場合でも、外側からは物理鍵で普通に開けられるので安心してください。物理鍵は絶対に持ち歩く、これが鉄則です。
また、両面テープの劣化などで本体が落下してしまった場合に備え、サムターンの高さ調整アダプターのネジはしっかり締めておきましょう。設置から24時間はテープの粘着力が最大になるまでそっとしておくのも、落下防止の秘訣です。
退去時に跡を残さず取り外す安全な方法
いざ引越しとなるとき、強力な両面テープをどう剥がすかは悩みどころです。無理に引っ張るとドアの塗装が剥がれる恐れがあります。
ドライヤーで接着面を温めて粘着剤を柔らかくし、デンタルフロスや釣り糸のような細くて丈夫な糸を隙間に入れて、ノコギリのように動かしながらゆっくり切るように外します。
残った糊(のり)は、市販のシール剥がし液や親指でこすればきれいに取れます。最初からマグネットアダプターを使っていれば、この手間は一切不要で、パカッと外すだけで完了です。

賃貸派にはやはりマグネットが最強の選択肢と言えます。
賃貸でのセサミスマートロック活用まとめ
今回は、賃貸住宅でも安心して導入できる「セサミスマートロック」について解説しました。工事不要で取り付けられ、アプリでの管理やオートロックなどの便利機能が充実しているセサミは、僕たち賃貸ユーザーにとって非常に心強いアイテムです。
最後に、この記事の要点をまとめます。
「鍵」という日常の小さなストレスをなくすだけで、生活の質はぐっと上がります。ぜひあなたのライフスタイルに合わせたスマートロックライフを始めてみてください!