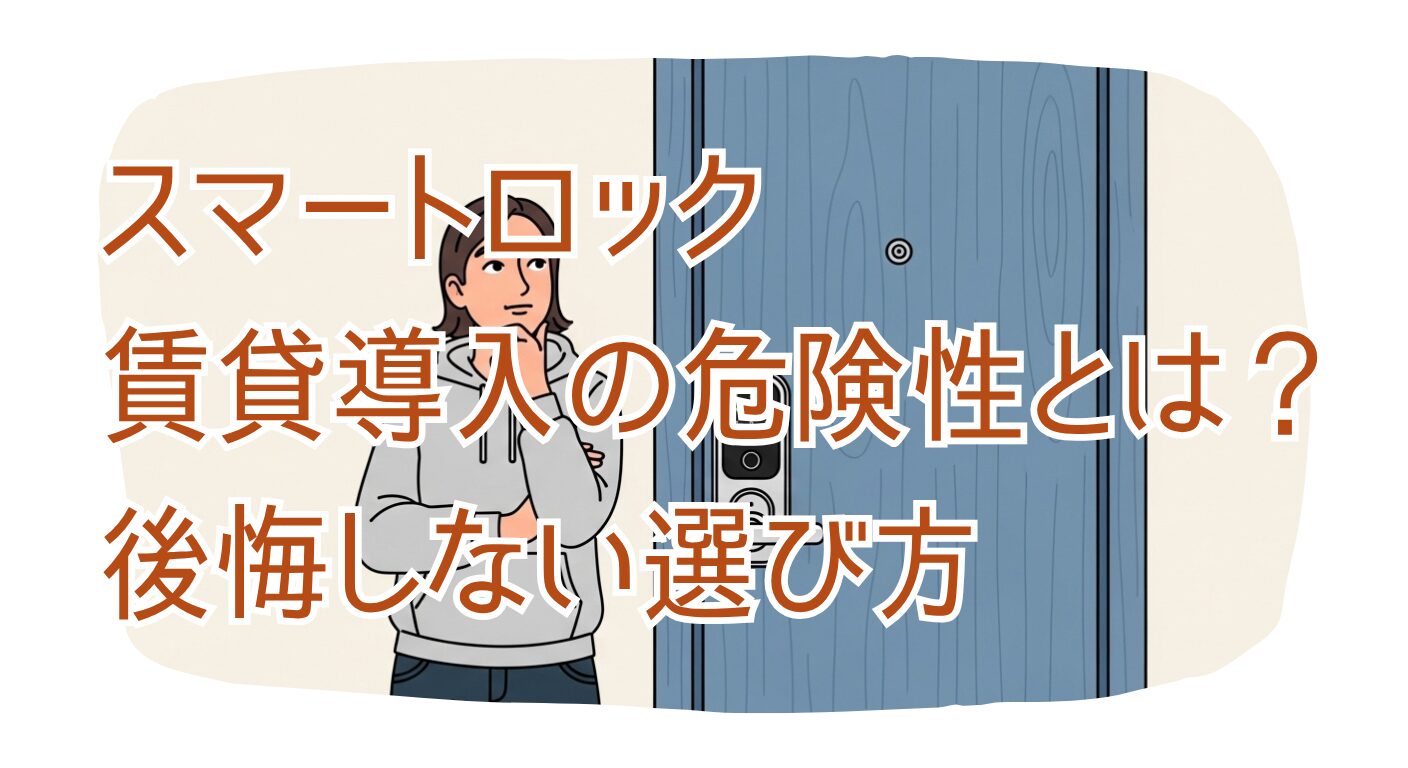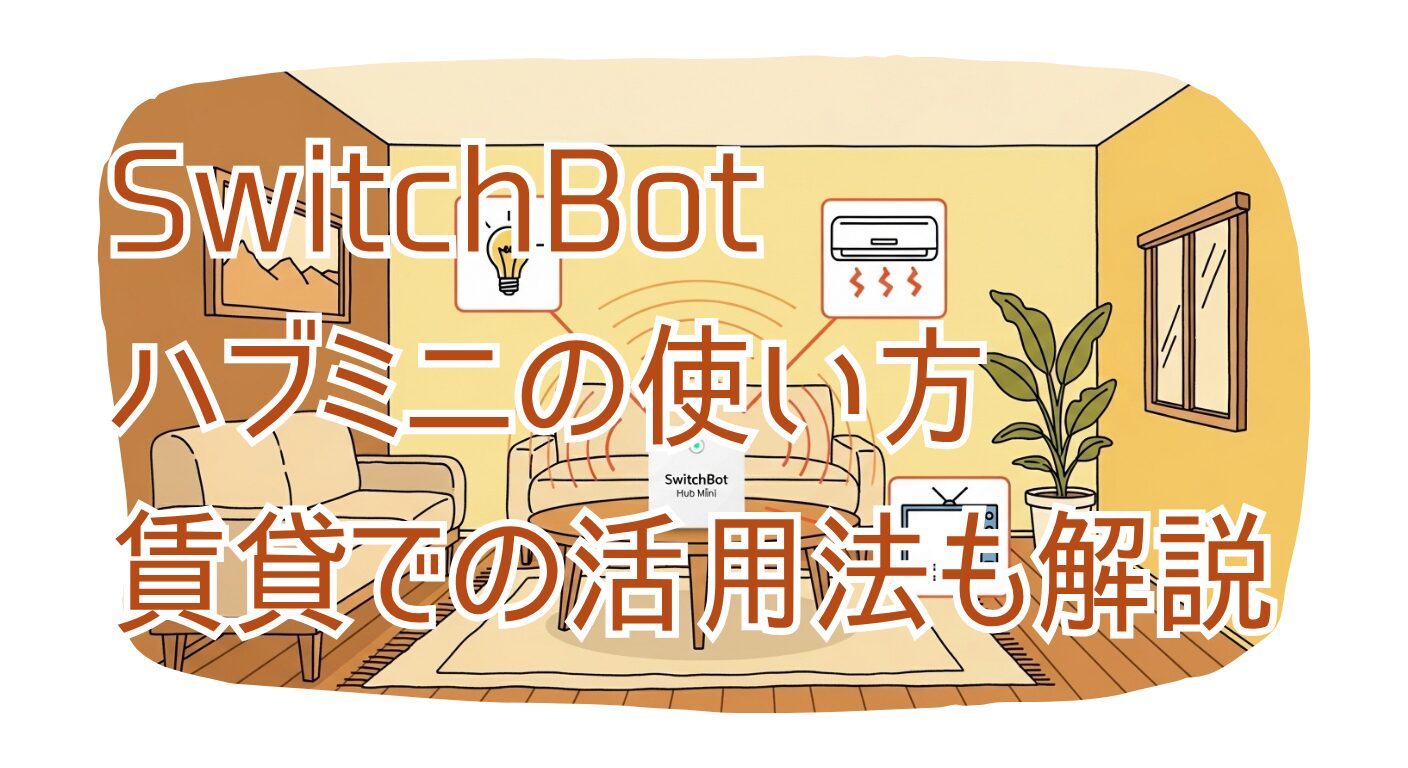スマホで鍵を開け閉めできるスマートロック、便利そうで憧れますよね。賃貸でも使える後付けタイプが増えて、導入を考えている人も多いと思います。
でも、いざ導入するとなると、賃貸ならではの危険性はないのか、後悔しないか不安になりませんか?例えば、ハッキングや不正アクセスのセキュリティ問題、急なバッテリー切れで家に入れなくなったらどうしよう、という心配。さらに賃貸だと、大家さんや管理会社への許可は必要なのか、退去時に原状回復で揉めないか、といった特有の悩みも出てきます。
僕もSwitchBotなどの製品を調べ始めた時、まったく同じ不安を感じていました。便利な反面、デメリットやリスクもしっかり理解しておかないと、取り返しのつかないトラブルになるかもしれません。この記事では、賃貸でスマートロックを導入する前に知っておくべき危険性や、後悔しないための対策を詳しく解説していきます。
記事のポイント
- スマートロックの主なセキュリティと技術的リスク
- 賃貸物件特有の契約や原状回復トラブル
- 後悔しないために確認すべき具体的な対策
- 賃貸で人気のSwitchBot製品の評判と注意点
スマートロックに潜む一般的な危険性
まずは、賃貸かどうかに関わらず、スマートロックという製品そのものが持つ「技術的な危険性」を見ていきましょう。便利さの裏側にあるリスクを知っておくことは大切です。
ハッキングや不正アクセスのセキュリティリスク
スマートロックはインターネットやBluetoothで通信するため、残念ながらハッキングのリスクはゼロではありません。
特に、価格が安すぎる製品や、セキュリティアップデートが提供されない海外メーカーの製品には注意が必要です。通信が暗号化されていなかったり、アプリ自体に脆弱性があったりすると、悪意のある第三者に通信を傍受され、解錠コードを盗まれる可能性も指摘されています。
もちろん、有名メーカーは暗号化技術などで対策していますが、私たち利用者が「パスワードを使い回さない」「アプリを常に最新版にする」といった自衛も不可欠です。
プライバシー監視の不安
これは特に、大家さんや管理会社が設置したスマートロックを利用する場合の懸念点です。
スマートロックは「誰が」「いつ」鍵を開け閉めしたか、すべてログ(履歴)が残ります。この入退室データを管理会社が閲覧できる場合、入居者の生活パターンが筒抜けになってしまう可能性があります。
「友人が泊まりに来たのがバレる」「不在の時間帯を把握される」といったプライバシーの問題は、かなり気分の良いものではありませんよね。自分で設置する場合でも、家族間でのプライバシー意識は確認しておいた方が良いかもしれません。
故障やバッテリー切れによる「締め出し」リスク
僕が一番怖いと感じているのが、この「締め出し」リスクです。
多くのスマートロックは電池で動いています。もし、電池が切れたら、当然ですがスマホや指紋では鍵が開きません。
「アプリに通知が来るから大丈夫」と思っていても、長期旅行中や、寒い冬の日に急に電池性能が落ちて切れてしまうケースも考えられます。
電池切れで家に入れなくなり、鍵屋(ロックスミス)を呼ぶと、数万円の思わぬ出費がかかることも…。また、Wi-FiやBluetoothの通信障害、スマホの充電切れ、アプリの不具合など、物理的な鍵では起こり得なかったトラブルで締め出される可能性もあります。
賃貸だからこそ注意すべき特有の危険性
次に、賃貸物件でスマートロックを使う場合、特有のトラブルや危険性について解説します。これは「持ち家」との大きな違いなので、必ずチェックしてください。
大家さん・管理会社との契約トラブル
最も重要なポイントです。賃貸物件はあくまで「借り物」です。
良かれと思って便利なスマートロックを設置しても、大家さんや管理会社に無断で設置した場合、契約違反とみなされる可能性があります。
緊急時に管理会社が物理鍵で入れない、火災報知器の点検業者が入れない、といった事態が発生すると、大きなトラブルに発展しかねません。最悪の場合、契約解除を求められるリスクもあります。
設置時のドア損傷と原状回復の問題
「工事不要」と書かれている製品でも、設置方法には注意が必要です。
スマートロックの中には、既存の鍵(シリンダー)を丸ごと交換するタイプや、ドアに新しく穴を開ける必要があるタイプも存在します。これらを無許可で行うと、退去時に「原状回復義務」を問われます。
ドアの交換費用は非常に高額になるため、賃貸物件では「穴あけ」や「既存の鍵の交換」が必須な製品は、絶対に避けるべきです。

賃貸の原状回復については、以下の記事で詳しく解説しているので、不安な方は合わせて読んでみてください。
両面テープの粘着跡と修繕費用
賃貸向けのスマートロックは、室内側のサムターン(鍵のつまみ)に、両面テープで貼り付けるタイプが主流です。
「テープなら大丈夫」と安心しがちですが、ここに落とし穴があります。強力な両面テープは、剥がすときにドアの塗装や表面のシートまで一緒に剥がしてしまう危険性があるんです。
特に古い物件や、デリケートな素材のドアの場合、粘着跡が残ったり、傷がついたりすると、退去時に修繕費用として敷金から引かれる原因になります。
賃貸で後悔しないために!導入前の対策と注意点
ここまで危険性ばかり話してきましたが、もちろん対策をしっかり行えば、スマートロックは非常に便利なアイテムです。賃貸で後悔しないために、導入前にやるべきことをまとめます。
最優先!大家さん・管理会社への事前許可
何をおいても、まずはこれです。スマートロックを設置したい旨を、必ず大家さんや管理会社に相談し、書面(メールなど記録が残る形)で許可をもらいましょう。
その際、以下の点を明確に伝えるとスムーズです。
- 設置したい製品の型番(パンフレットやURLを共有)
- 「工事不要」で「両面テープ」で固定するタイプであること
- ドアに一切穴を開けたり、傷つけたりしないこと
- 退去時には必ず元通りに撤去すること(原状回復)
- 緊急時(火災や本人の安否確認など)の管理会社の立ち入りにどう対応するか(例:物理鍵も別途渡しておく、など)
許可さえ得ておけば、最大のトラブルである契約違反のリスクは回避できます。
必ず「工事不要の後付け型」を選ぶ
賃貸で選ぶべきは、室内側のサムターンの上から被せて両面テープで固定するタイプ(後付け型)一択です。
これなら、既存の鍵はそのまま残せますし、退去時の撤去も(比較的)簡単です。SwitchBotやQrio、SESAMEなどがこのタイプの代表的な製品ですね。
間違っても、鍵穴ごと交換するタイプや、ドアに穴を開けるタイプは選ばないでください。
- 既存の鍵(物理鍵)もそのまま使える
- ドアを傷つけないため原状回復が容易
- 設置が自分で簡単にできる
締め出し対策!物理鍵のバックアップは必須
スマートロックを導入しても、物理鍵(今までの鍵)は絶対に捨てないでください。
「スマホがあるから大丈夫」と油断し、物理鍵を持ち歩かなくなった瞬間に、以下のトラブルが起こる可能性があります。
- スマートロック本体の電池切れ
- スマホの充電切れ
- スマホの紛失・故障
- アプリや通信の不具合
「財布やカバンに物理鍵を1本忍ばせておく」「実家や信頼できる友人に預けておく」など、万が一の締め出しに備えたバックアップ(緊急解錠手段)は必ず用意しておきましょう。
賃貸で人気の「SwitchBot」はどう?危険性や評判
賃貸向けスマートロックとして、僕も注目しているのが「SwitchBot」シリーズです。価格も手頃で、後付け型なので賃貸ユーザーに大人気ですよね。では、SwitchBot製品特有の危険性や評判はどうでしょうか。
SwitchBotスマートロックの仕組みと安全性
SwitchBotロック(Proなど)は、まさに賃貸向きの「両面テープで貼り付ける後付け型」です。サムターンの形状に合わせてアタッチメントが調整できるため、多くの賃貸物件のドアに対応できるのが強みです。
セキュリティ面では、通信は暗号化されていますし、国際的な規格(ISO/IEC 27001)にも準拠していると公表されており、一定の信頼性はあります。
ただし、過去にはSwitchBotのアプリに脆弱性が見つかった(現在は修正済み)ケースもあるため、アプリを常に最新版にアップデートしておくことは、利用者の義務として重要です。
実際の評判とよくある不具合(口コミ)
便利な反面、もちろん悪い評判や不具合の報告もあります。
良い評判・口コミ
悪い評判・不具合の報告
特に多いのが、物理的な「位置ズレ」や「落下」に関するトラブルのようです。また、電池切れやアプリの不具合による締め出しリスクは、SwitchBot製品も例外ではありません。
SwitchBot製品に限らず、後付け型スマートロックは、取り付け位置の調整がシビアです。少しズレるだけで動作不良の原因になります。また、両面テープの劣化には注意し、万が一の物理鍵は必ず持ち歩くようにしましょう。
まとめ:危険性を理解し、許可を得て賃貸スマートライフを!
今回は、賃貸でスマートロックを導入する際の危険性や注意点について解説しました。
スマートロックは非常に便利ですが、「セキュリティリスク」「締め出しリスク」そして賃貸特有の「契約・原状回復リスク」という3つの危険性があります。
これらのリスクをしっかり理解した上で、
この3点を守ることが、後悔しないための絶対条件です。
ちなみに、スマートロック以外にも賃貸で始められるスマートホーム機器はたくさんあります。まずは簡単なところから試してみるのも良いかもしれませんね。

賃貸でスマートホームを始める第一歩については、以下の記事もぜひ読んでみてください!